

ソニーコンピュータサイエンス研究所シニアリサーチャー。東京大学特任教授(共創研究室、Collective Intelligence Research Laboratory)。東京大学大学院理学系研究科物理学専攻課程修了、理学博士。理系と法学の両分野にまたがる学際的な学問的背景を有する。神経科学、意識研究、人工知能分野における長年の研究実績を持つ。理化学研究所、ケンブリッジ大学などの権威ある機関で研究職を歴任。
主な研究テーマは、意識の神経科学、クオリア、人工知能、創造性、認知科学と文化・技術の交差領域。科学コミュニケーションや教育活動、分野横断的な研究推進にも積極的に取り組んでいる。屋久島おおぞら高校校長として、全人教育と革新的な学習環境の構築に尽力している。
著書多数。『脳と仮想』で第4回小林秀雄賞。 『今、ここからすべての場所へ』 で第12回桑原武夫学芸賞 を受賞。近著 『クオリアと人工意識』 は29言語に翻訳され、31か国で刊行。意識とテクノロジーに関する国際的議論における主要な発信者の一人。
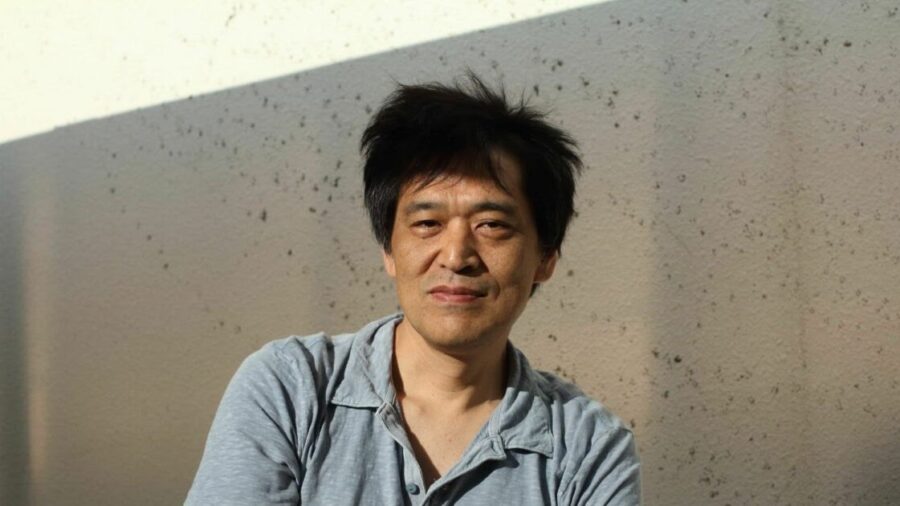
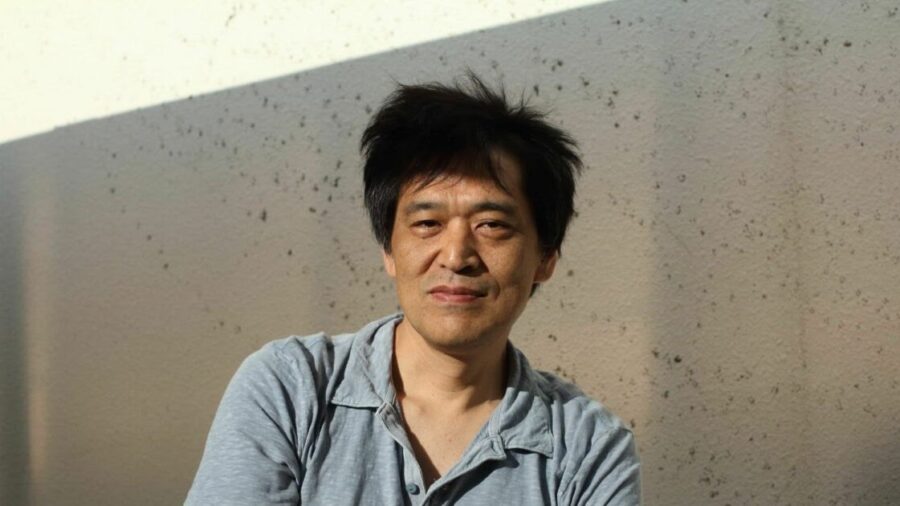
東京大学大学院総合文化研究科・広域科学システム系教授。理学博士。複雑系・人工生命研究の第一人者。20年以上にわたる学術・研究キャリアを通じて、物理学、ロボティクス、コンピュータシミュレーション、生化学実験などを融合した学際的アプローチにより、生命らしさをもつシステムの探究に取り組む。主な研究テーマは、遺伝暗号の進化、突然変異ダイナミクス、相互接続されたシステムにおける認知的複雑性、人工エージェントにおける自律性とエナクションの実現など。
科学と芸術の融合に積極的に取り組み、創発的な振る舞いを探るヒューマノイドアンドロイド「Alter3」や群体行動を再現する大規模Boidsモデルなど、先駆的なプロジェクトを多数主導。人工知能と生命類似システムの境界を拡張することを目的とした企業「Alternative Machine」の創設者。2018年に東京で開催された人工生命国際会議(ALIFE 2018)では、主催者として中心的役割を担い、同分野への貢献を果たす。
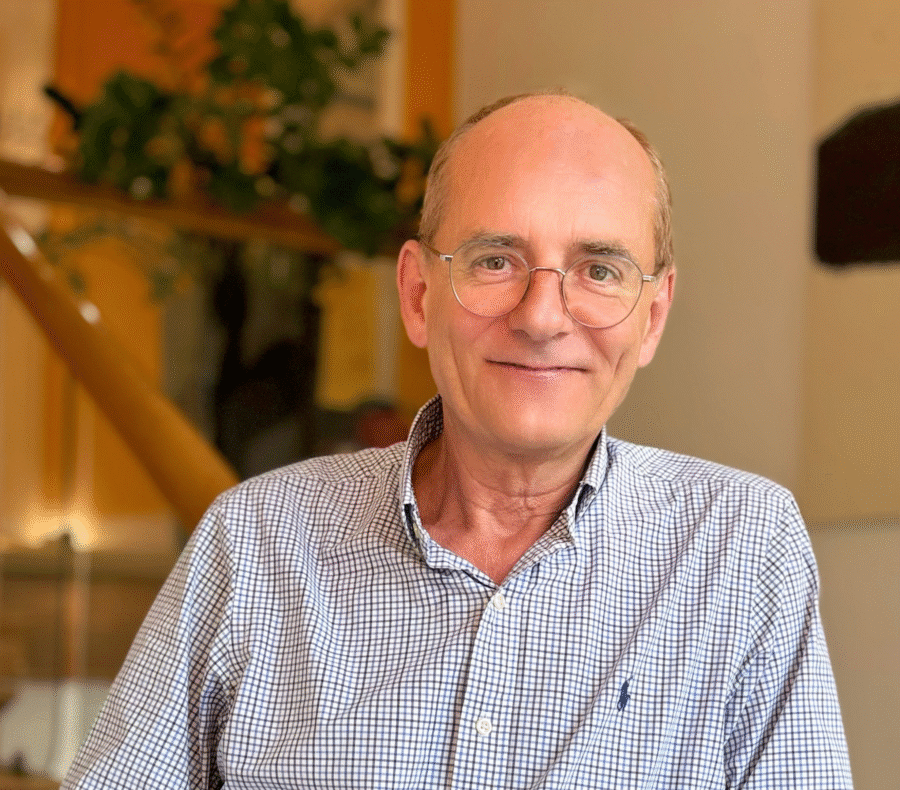
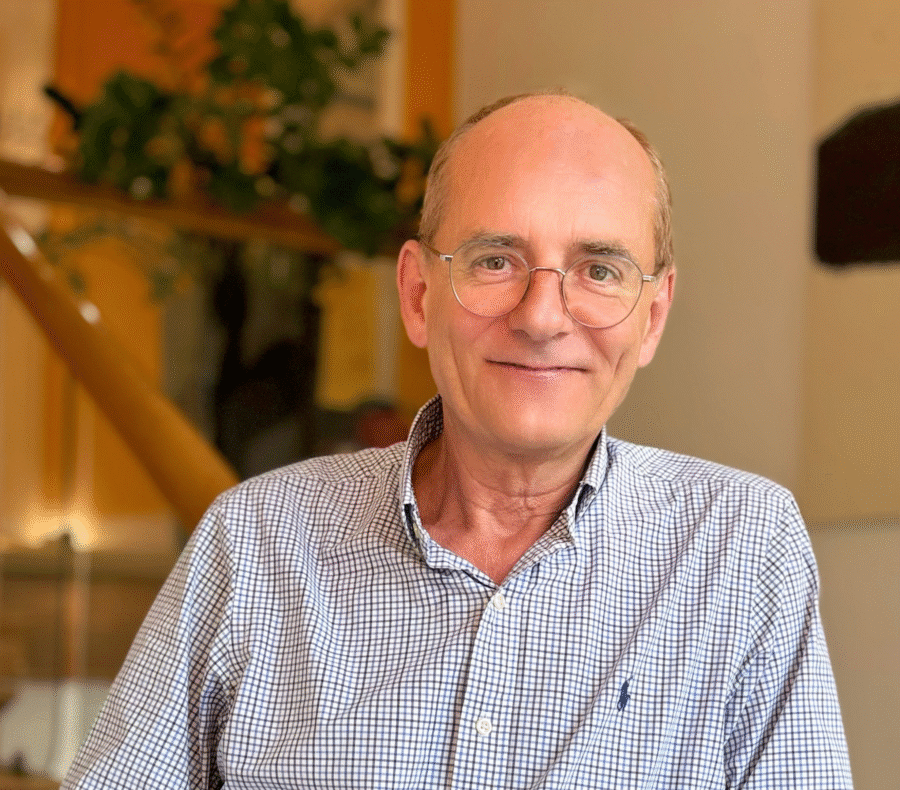
ジュネーブ大学の神経科学教授。「All Here」のチーフ神経科学ディレクターとして、EEGを用いた機能的脳マッピングの豊富な専門知識を活かし、瞑想に関する神経イメージング研究の設計・実施・解析を統括。神経科学の分野で国際的に知られるリーダー的存在。
2007年より学術誌『Brain Topography』の編集長を務めるほか、2013〜2015年にはスイス神経科学会会長、2012〜2014年には国際脳電磁気学会会長、2008〜2015年にはスイスてんかん協会の理事を歴任。


Prof. Karlheinz Krause is President of the Geneva Foundation for Medical Research and Emeritus Professor in the Department of Pathology and Immunology at the University of Geneva Faculty of Medicine.
He has published extensively in leading international journals and holds numerous patents. His highly cited work has advanced understanding of oxidative stress biology, central nervous system physiology, and the biotechnological applications of pluripotent stem cells. His current research focuses on cell and gene therapy, with particular emphasis on gene therapy vectors and cell-based therapies for Parkinson’s disease.
He earned his MD from Ludwig Maximilians University in Munich and trained in internal medicine and infectious diseases in Geneva and the United States. An elected member of both the Swiss Academy of Medical Sciences and the American Society for Clinical Investigation, he actively contributes to translational research and supports the development of innovative biomedical technologies.


ヨガ指導者として世界的に知られ、インド国家勲章パドマシュリーを授与される。ヴィヴェーカーナンダ・ヨーガ研究財団(VYASA)の会長。スワミ・ヴィヴェーカーナンダ・ヨーガ研究大学(S-VYASA大学)の総長。バンガロール大学(現・ベンガルール大学)で機械工学の学士号、インド科学研究所(IISc)で機械工学の博士号を取得(1968年)。その後、IIScの教員、カナダ・ブリティッシュコロンビア大学の博士研究員、米国ハーバード大学工学科学研究所のコンサルタントとして活躍している。
1975年以降、ヴィヴェーカーナンダ・ケーンドラと関わりを持ち、ヨーガ療法・研究委員会の名誉ディレクター、事務局長などを歴任。2000年よりヴィヴェーカーナンダ・ヨーガ研究財団(VYASA)の会長、2002年から2013年まではスワミ・ヴィヴェーカーナンダ・ヨーガ研究大学(S-VYASA大学)の副総長を務める。現在は同大学の総長。ヨーガの学術的発展における中心的存在。
工学分野での論文発表30本、ヨーガに関する論文135本、著書28冊。博士課程の学生32名を指導。KIIT(ブバネーシュワル)から名誉理学博士号(DSc, Honoris Causa)を授与される。ヨーガ・シュリー賞、バーラト・ガウラヴ賞など、受賞歴も多数。政府および民間の委員会にて委員長や委員を歴任。世界各地でのヨーガ教育推進に尽力し、心身の健康と調和を追求する分野におけるリーダーシップを体現している。


インド・ベンガルールのS-VYASA大学にて、副総長、研究担当ディレクター。自然療法・ヨーガ科学の学士号、博士号、理学博士号を取得。学術・研究・運営における28年の経験を持つ。国際的な学術データベースに登録されたジャーナルに84本の論文を発表。研究テーマはヨーガの心理生理学、瞑想の神経相関、老化、リハビリテーション。国際ヨーガ学術誌(IJOY)編集長。国際誌多数の査読者。ハーバード医科大学、モナシュ大学、ロンドン王立医学会、上海体育大学、イタリア・ファーマ大学などで講義・ワークショップを担当。
インド政府 科学技術省 科学諮問委員会委員。Niti Aayog 統合医療イニシアティブ研究諮問委員。NAAC ヨーガ高等教育認定コア委員。中国・雲南民族大学 ヨーガ認定プログラム運営委員。ヴィヴェーカーナンダ・ヨーガ大学(米国)副学長、アジアヨーガ療法協会(シンガポール)副会長。統合医療クリニック&病院「Vivekananda Health Global」創設ディレクター。英議会下院「Bharat Gaurav Award」、ASTAMヨーガ・フォーラム(ミュンヘン)「パタンジャリ賞」など受賞歴多数。


スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)Neuro-X研究所およびBrain-Mind研究所にて、ベルタレッリ財団「認知神経補綴」講座を担当。ジュネーブ・キャンパスバイオテック内の認知神経科学研究室の所長。
EPFLの神経補綴センターの創設者・元センター長。ジュネーブ大学病院の客員教授。意識と身体感覚の神経科学、ヒトの能力拡張、個別化医療を専門とする。ロボティクスやVR(バーチャルリアリティ)を用いた意識研究・認知心理学の先駆者。神経変性疾患(パーキンソン病、認知症)、メンタルヘルス、ウェルビーイングの分野における、予防・診断・治療に向けた医療応用研究にも注力。エルキン・ベクと協力し、没入型テクノロジーと神経科学によるモニタリングを融合した瞑想体験プラットフォーム「Home Within: Meditation Neuro-engineering Journey」の開発を主導。


インドにおいて、ヨーガおよび自然療法の資格を有する医師・指導者。INYGMA(インド自然療法・ヨーガ卒業生医学協会)にてシニア副会長を務めるほか、Sammati Wellbeing Centreのディレクターを務める。
国際自然療法医学会議(ICNM)の実行委員会メンバーを歴任。2019年にインド・グレーター・ノイダで開催された「世界アーユルヴェーダ・ヨーガ・自然療法会議(WAAYN)」の発起人。
著者、講演者、企業向けウェルネスコンサルタントとしても活動。


韓国出身・在住の画家。代表作「Brush(筆)」シリーズで知られ、東洋と西洋の調和的な共存を象徴する作品を描いている。中国伝統の書道筆が東洋の精神文化を、写実的な表現技法が西洋美術の特徴をそれぞれ表現しており、その融合が静寂と調和の極致を体現している。東西の対極を見事に同期させるイ・ジョンウンの卓越した技量により、「Brush」シリーズは、人間の内なる力を静かに映し出している。
こちらをクリックすると『Behind The Art:Lee Jung Woong』をご覧いただけます。 あわせて彼の作品についても詳しくご確認いただけます。


ラケシュ・チャウラシアは世界的に著名な音楽家・作曲家であり、現代のバンスリ(インド亜大陸の横笛)の革新的な奏者である。彼は音楽の瞑想的・治療的側面に強い関心を寄せている。
幼少期から神童として知られ、伝説的な叔父であり笛の巨匠パンディット・ハリプラサド・チャウラシアの最も優れた弟子であるラケシュは、チャウラシア家の伝統を新たな高みへと導く確かな素質を示している。
日本、オーストラリア、ヨーロッパ、南アフリカ、アメリカなど世界各地のクラシックおよびセミクラシックコンサートで聴衆を魅了してきた。アテネのWOMADやロシア・日本・アメリカ・ヨーロッパでの「インド音楽祭」といった著名なフェスティバルにも定期的に出演し、パリのサン=ドニ音楽祭やイギリスのレスター国際音楽祭などではソロ演奏を披露している。また、エリザベス女王陛下の即位25周年を記念したBBCラジオの24時間生放送音楽番組ではフィナーレを務める。
インド映画界を代表する名だたる音楽家たちと多数の録音を重ねてきた。共同制作アルバム As We Speak』 は2024年にグラミー賞を2部門で受賞。受賞歴も多岐にわたり、2007年にはA.P.J.アブドゥル・カラム大統領よりインディアン・ミュージック・アカデミー賞を受賞。続いて2008年にアディティア・ビルラ・カラキラン・プルスカル、2011年にグル・シシヤ賞、そして2024年にはナクシャトラ・サンマンに輝いている。
エルキンと協働で探求を重ね、「The Silent Flute(ザ・サイレント・フルート)」を創作。これは、フルートの響きを通して“沈黙の音”の力を呼び覚ますことを目指すプロジェクトである。


幼少期よりバンスリーの演奏とヒンドゥスターニー音楽の奥義を学ぶ。 2002年から2009年まで、ヴィリンダーヴァン・グルクラ(伝統的な音楽教育期間)にて、パンディット・ハリプラサード・チャウラシア氏の直接指導を受けながら、共に数多くのコンサートにも出演。
現在は、自らのスタイルを磨きながら、インドやヨーロッパにてソロ演奏を行うほか、グルグラム(NCR)にあるインターナショナル・バンスリー・アカデミーにてフルート講師を務める。 また、父とともに製作するプロフェッショナル・バンスリーは、世界中の奏者に愛用されている。


瞑想における意識の探究、精神への影響、科学とのつながりに強い関心を寄せる、経験豊かなスイスの法律家。スイスおよび海外のバイオテクノロジー分野で培った豊富な経験と、「All Here」の理念への深い共感を背景に、瞑想という流動的な領域と、法制度という科学的枠組みの間に生じるギャップを橋渡しする役割を担っている。


1559年に設立された、スイスを代表する名門の国立研究大学。多様な分野にわたる教育・研究プログラムで知られています。
ヨーロッパを代表する理工系大学のひとつ。最先端の研究、革新、教育への取り組みで高く評価されています。
The Laboratory of Cognitive Neuroscience (LNCO) at EPFL is a research facility within its Neuro X Institute that focuses on advancing our understanding of the neu-ral mechanisms underlying cognition and behavior. The laboratory engages in interdisciplinary research, combining neuroscience, psychology, and technology to explore various aspects of cognitive processes. It plays a crucial role in advancing our understanding of the brain and cognition, contributing to both basic scientific knowledge and the development of applications that benefit society.
東京大学は日本を代表する研究機関であり、アジアでもトップクラスの学術機関として、科学・技術・人文分野における革新的な研究で国際的に高く評価されています。脳科学、認知科学、複雑系など、さまざまな分野を横断する研究が行われています。
東京大学共創研究室では、All Hereとの共同研究として、「生きがい」の概念に加え、脳科学・認知科学・AIの知見を組み合わせることで、瞑想の効果をより深め、広げる方法を探求しています。また、人工生命やダイナミカル・システム(動的システム)という視点から、瞑想体験の中核にある「自己」の本質を解明しようとしています。


インド・ベンガルールにある名門の高等教育機関。ヨーガの研究と治療に特化しています。All Here は S-VYASA 大学と連携し、瞑想、ヨーガ、そして関連する科学分野の研究と教育の発展を目指しています。
現在のところ、深い瞑想状態を客観的に測定する国際的な基準は確立されていません。All Here と S-VYASA大学はこの課題に取り組むべく、インドおよび世界各地の伝統的な実践に基づいた高度な瞑想段階の研究を共同で進めています。
さらに、セミナーや学術会議などの実演イベントを通じて、インド、スイス、そして国際的な研究者同士の連携を深める計画も進めています。
神経生理学分野における世界的なリーダーであり、最先端の脳波(EEG)システムや脳マッピング技術で知られる企業。高性能で柔軟性の高い機器は、臨床や研究の現場で世界中の専門家に活用され、脳や認知機能に関する貴重な知見をもたらしています。
ANT Neuroは、瞑想中の脳活動を可視化する先進的なEEGシステムをAll Hereに導入しています。これにより、科学的に開発された手法が脳に与える影響をより深く理解し、瞑想状態を数値として捉えることが可能になります。ANT Neuroとの連携により、All Hereは瞑想を次のステージへと進化させています。現代の神経科学と、古くから伝わる瞑想の実践を融合させることで、新しい世代の実践者をサポートしています。
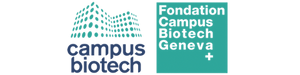
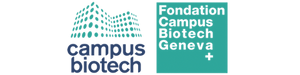
ジュネーブ・キャンパス・バイオテック財団(FCBG)は、ジュネーブにおける生命科学研究、バイオ・ニューロエンジニアリング、トランスレーショナル・イノベーションの卓越した研究拠点の創設に尽力する主要な非営利組織です。
2013年にEPFL、ジュネーブ大学、ジュネーブ州が共同で設立した FCBGは、スイス国立研究能力センターとして認められており、 学術研究グループ、産業パートナー、スタートアップ企業に対し、最先端の研究インフラ、共有プラットフォーム、共同研究支援を提供しています。
基本神経科学、工学、デジタルヘルス分野における相乗効果を促進し、バイオエンジニアリング分野における影響力の大きい統合的研究を可能にすることを理念としています。
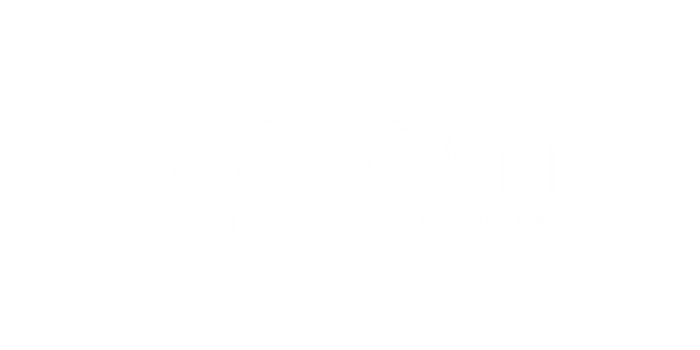
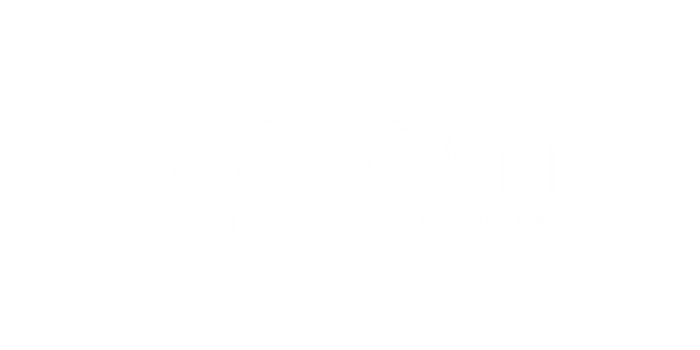
CSEMは、マイクロテクノロジー、精密製造、人工知能、持続可能なエネルギー分野におけるイノベーションを推進する、スイスの主要な応用研究・技術機関です。
協力機関と緊密に連携し、科学的なブレークスルーを実用的な解決策へと転換することで、技術の発展と社会への貢献を推進しています。